2014楽天オープンREPORT

 USオープンで準優勝し、続くクアラルンプール大会では優勝。そして母国開催の楽天ジャパンオープンのために帰国した錦織 圭を、各メディアは「凱旋帰国」という言葉で迎えた。当然、国内の注目度は非常に高く、大会のチケットは連日ソールドアウト。また錦織は、クアラルンプール大会前に香港に立ち寄り、ATPが「アジアン・スイング」と名付けた秋のシリーズの顔として各種プロモーションに参加。今や、男子プロテニス選手を代表する顔としての役割も求められるようになってきた。
USオープンで準優勝し、続くクアラルンプール大会では優勝。そして母国開催の楽天ジャパンオープンのために帰国した錦織 圭を、各メディアは「凱旋帰国」という言葉で迎えた。当然、国内の注目度は非常に高く、大会のチケットは連日ソールドアウト。また錦織は、クアラルンプール大会前に香港に立ち寄り、ATPが「アジアン・スイング」と名付けた秋のシリーズの顔として各種プロモーションに参加。今や、男子プロテニス選手を代表する顔としての役割も求められるようになってきた。
その錦織、フィジカルが強くなったとはいえ178cmという体格で世界トップのパワーヒッターたちを打ち破り続けるのは並大抵のことではない。USオープンから続く連戦で、楽天オープンの時には心身の疲労はピークに近かっただろう。それでも錦織は勝った。特に際立っていたのは、≪取るべきポイントを取り、落としてはいけないポイントを落とさない≫ということ。そうした傾向は2月のデ杯カナダ戦の頃にはすでに見え隠れしていたのだが、今回の錦織はポイントやゲームの≪落とし方≫が格段に上達していた。試合を通じてダメージ・コントロールをし、相手にある程度打たせつつも流れは渡さない。そして『ここを取れば』というポイントではきっちりとギアを上げてモノにして試合を勝利でまとめあげる。トッププロたちは皆、当たり前にやっていることだが、言葉で言うよりずっと困難なことを今の錦織はやってのけている。『本物のトップ10選手の凄み』とでも言うべきものだろう。

それでも相手が強くなれば全開の時間帯を増やさざるを得ない。準々決勝のシャルディ戦あたりまではまだ余裕も感じられたが、準決勝のベッカー戦になると、その余裕も消え始めていた。「シャルディ戦の頃にはもう限界を超えていた」と錦織は話しているが、ベッカー戦で第1セットを落としたのが、この大会で唯一のミステイクだった。その後きっちりと立て直して勝利はしたものの、USオープン後にデ杯に出ただけで調整万全のラオニッチにはかなりの苦戦も予想された。開幕前、「今年は今まで以上の成績を狙いたい」と話していたラオニッチは、過去2年連続で準優勝。彼の言う≪上≫は優勝しかない。選手から強気な言葉が出るときというのは、それだけ自信がある証拠でもある。
 だが、錦織はラオニッチを再び倒した。スコアは7-6(5)、4-6、6-4。お互いにブレークは一度ずつで、トータルポイントでも97対96とわずか1ポイントの差だったが、錦織はこの試合でも≪取るべきポイント≫をきっちりと自分のモノにした。全体を俯瞰して見ると、錦織が第3セットの最後となったゲームまで試合をイーブンに維持し続け、ゴール寸前でアクセルを床まで踏み込んだという印象の試合だったが、それまでエースを奪われていたラオニッチの強烈なサービスに対して、最後は単に食らいつくだけでなく、わずかな面の操作で反撃不能の位置にリターンしたのも錦織が≪勝利をものにするためのギア≫を上げたから。勝つべくしてトーナメントを制した、本当に強い選手の勝ち方だった。
だが、錦織はラオニッチを再び倒した。スコアは7-6(5)、4-6、6-4。お互いにブレークは一度ずつで、トータルポイントでも97対96とわずか1ポイントの差だったが、錦織はこの試合でも≪取るべきポイント≫をきっちりと自分のモノにした。全体を俯瞰して見ると、錦織が第3セットの最後となったゲームまで試合をイーブンに維持し続け、ゴール寸前でアクセルを床まで踏み込んだという印象の試合だったが、それまでエースを奪われていたラオニッチの強烈なサービスに対して、最後は単に食らいつくだけでなく、わずかな面の操作で反撃不能の位置にリターンしたのも錦織が≪勝利をものにするためのギア≫を上げたから。勝つべくしてトーナメントを制した、本当に強い選手の勝ち方だった。
だが、もちろん課題もある。錦織にとってトップ5はすでに射程距離。グランドスラム決勝も経験した以上、残る頂点はグランドスラム優勝かランキングNo.1の座だけ。そのためのカギを錦織本人は「体力面がポイントになると思います」と語っているが、事実、楽天オープンで精根尽きた感じになった錦織は、翌週の上海マスターズでは初戦負け(1回戦BYEの2回戦)。しかし、日本のテニスファンの常識を常に覆してきたのが錦織。彼なら成し遂げるだろうと思いつつも、それがいったいどんな形で実現されるのか。そのときの錦織のテニスを早く見てみたい。そんな気にさせられたのが今年の楽天オープンだった。
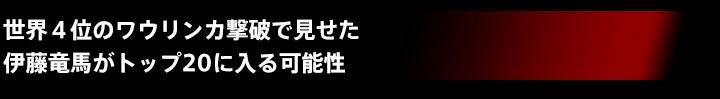
 1回戦で今年の全豪オープンの覇者スタニスラス・ワウリンカを破った伊藤竜馬。ワウリンカのランキングは4位。錦織が残したものを除けば、日本男子テニス史上でも歴史的な番狂わせだ。今はドイツを拠点に練習をしている伊藤は「ジル・シモンやヤルコ・ニーミネンなどと一緒にトレーニングを積む機会が増えている」と言うのだが、彼はそのなかで「トップ10を経験した選手でも、そんなに変わらないという実感が出てきた」とワウリンカ戦後に話していた。今の男子トップ100前後の選手たちのレベルは高く、決定的な弱点を抱えたままではトップ100には入れない。しかし一旦トップ100に入ると、トップの数人を除けば、トップ20以下は技術的にそう大差があるわけではない。差が出るのは、勝負所でのわずかなショットの精度や精神的な余裕が生む試合全体をマネージメントする力。伊藤はそれを実感として持つことで、持ち前の実力を試合で発揮できるようになってきている。
1回戦で今年の全豪オープンの覇者スタニスラス・ワウリンカを破った伊藤竜馬。ワウリンカのランキングは4位。錦織が残したものを除けば、日本男子テニス史上でも歴史的な番狂わせだ。今はドイツを拠点に練習をしている伊藤は「ジル・シモンやヤルコ・ニーミネンなどと一緒にトレーニングを積む機会が増えている」と言うのだが、彼はそのなかで「トップ10を経験した選手でも、そんなに変わらないという実感が出てきた」とワウリンカ戦後に話していた。今の男子トップ100前後の選手たちのレベルは高く、決定的な弱点を抱えたままではトップ100には入れない。しかし一旦トップ100に入ると、トップの数人を除けば、トップ20以下は技術的にそう大差があるわけではない。差が出るのは、勝負所でのわずかなショットの精度や精神的な余裕が生む試合全体をマネージメントする力。伊藤はそれを実感として持つことで、持ち前の実力を試合で発揮できるようになってきている。
 元々、伊藤はサービスとフォアのパワーでは日本男子でもトップクラス。この二つだけでなら、錦織との比較でもいい勝負というところだろうが、問題はその力を出せるかどうか。ワウリンカ戦での伊藤は第1セットも第2セットも先にブレークして先行することで、さらに心の余裕を持ち、いい意味での上から目線で相手を飲み込んだ。試合後「相手が最初の段階でナーバスになっているのがわかった」とコメントした伊藤は、「ドローが決まったときから、勝つイメージを強く自分の中に描いて強い気持ちで戦い抜いた」という。「相手はグランドスラムに勝っている選手。でも、自分もそういう舞台に立ちたい。そういう選手を倒していかないとダメ。相手を上に見過ぎず対戦したのが良かった」と言う伊藤は、ある意味シンプルな心境でコートに立ち無心で勝利を目指せていたのだろう。
元々、伊藤はサービスとフォアのパワーでは日本男子でもトップクラス。この二つだけでなら、錦織との比較でもいい勝負というところだろうが、問題はその力を出せるかどうか。ワウリンカ戦での伊藤は第1セットも第2セットも先にブレークして先行することで、さらに心の余裕を持ち、いい意味での上から目線で相手を飲み込んだ。試合後「相手が最初の段階でナーバスになっているのがわかった」とコメントした伊藤は、「ドローが決まったときから、勝つイメージを強く自分の中に描いて強い気持ちで戦い抜いた」という。「相手はグランドスラムに勝っている選手。でも、自分もそういう舞台に立ちたい。そういう選手を倒していかないとダメ。相手を上に見過ぎず対戦したのが良かった」と言う伊藤は、ある意味シンプルな心境でコートに立ち無心で勝利を目指せていたのだろう。
しかし、2回戦のベンジャミン・ベッカー戦では一転、伊藤の良さがほとんど出せないまま敗れてしまった。「力みがあった」と後に伊藤も話していたが、大きな番狂わせを演じた直後の選手というのはどうしても欲が出る。ベテランのベッカーはそれを見透かしたようにラリーをつなげ、伊藤のミスを誘った。
今の伊藤には一つでも多くの成功体験を積み上げることが必要だ。『これは使える』という何かを自分の中に溜めていくことがそのまま自信になる。「まずはトップ50を切りたい。それはできると思う。目標としてはトップ20を超えたい。グランドスラムでシードが付くような、そういう選手になりたい」と断言した伊藤。デビューしたての若手の言葉ではなく、既にツアーで経験を積んだ選手が言うこととしては大き過ぎるような気もするが、今の彼にはその道筋が見えてきているからこそ出て来た言葉なのだろう。

 シングルスは予選決勝で敗退したものの、錦織とのダブルスではダブルス・スペシャリストのフィルステンバーグとユーイのペアをストレートで下したのが内山靖崇。ダブルスのことばかりを持ち上げられるのは本人としては不本意かもしれないが、内山のダブルスのスキルは今や日本男子ではトップと言っていいだろう。2月のデ杯カナダ戦でも錦織とのペアでネスター・ダンセビッチ組という強敵を倒して日本のベスト8入りの原動力となったのが内山のダブルス。錦織・内山のペアは言わば「日本の切り札」と言ってもいいレベルになっている。錦織のリターンを含めた個人技の高さは言うまでもないが、内山がそれを完璧に補完して動き、同時に錦織の質の高いボールを生かす動きが出来ているため、自分のプレーにも余裕が生まれ、いい循環で試合が進む。『どんなペアが相手でも勝負に持ち込める』という自信が、この2人のペアからは漂っている。
シングルスは予選決勝で敗退したものの、錦織とのダブルスではダブルス・スペシャリストのフィルステンバーグとユーイのペアをストレートで下したのが内山靖崇。ダブルスのことばかりを持ち上げられるのは本人としては不本意かもしれないが、内山のダブルスのスキルは今や日本男子ではトップと言っていいだろう。2月のデ杯カナダ戦でも錦織とのペアでネスター・ダンセビッチ組という強敵を倒して日本のベスト8入りの原動力となったのが内山のダブルス。錦織・内山のペアは言わば「日本の切り札」と言ってもいいレベルになっている。錦織のリターンを含めた個人技の高さは言うまでもないが、内山がそれを完璧に補完して動き、同時に錦織の質の高いボールを生かす動きが出来ているため、自分のプレーにも余裕が生まれ、いい循環で試合が進む。『どんなペアが相手でも勝負に持ち込める』という自信が、この2人のペアからは漂っている。
 内山からすれば、ダブルスで見せる視野の広さや精神的な余裕、圧倒的と言ってもいいスピードをもっとシングルスでも生かせるようになれば、フィジカルの強さやショットの技術などはすでに一通りのものを持っているので、いつ結果が出ても不思議ではないというレベルにすでにきている。本物の自信は勝つことでしか得られないかもしれないが、内山の場合はむしろ、もっと思い上がるぐらいでちょうどなのかもしれない。「遠慮してやってしまうと負担になる」と錦織とのダブルスで見せた大胆さを、シングルスでも出して戦うことができれば、必ず結果もついてくるはずだ。
内山からすれば、ダブルスで見せる視野の広さや精神的な余裕、圧倒的と言ってもいいスピードをもっとシングルスでも生かせるようになれば、フィジカルの強さやショットの技術などはすでに一通りのものを持っているので、いつ結果が出ても不思議ではないというレベルにすでにきている。本物の自信は勝つことでしか得られないかもしれないが、内山の場合はむしろ、もっと思い上がるぐらいでちょうどなのかもしれない。「遠慮してやってしまうと負担になる」と錦織とのダブルスで見せた大胆さを、シングルスでも出して戦うことができれば、必ず結果もついてくるはずだ。
 USオープン・ジュニアのダブルスで優勝。錦織同様、≪凱旋帰国≫だったのは中川直樹も同じだった。そして予選のワイルドカードを得て、ツアーレベルの大会に初参戦。しかし1回戦の相手は、内山靖崇。同じIMGアカデミーの出身で、お互いのことを知り尽くした先輩後輩の対決は、6-1、3-6、6-3のフルセットで内山が制した。
USオープン・ジュニアのダブルスで優勝。錦織同様、≪凱旋帰国≫だったのは中川直樹も同じだった。そして予選のワイルドカードを得て、ツアーレベルの大会に初参戦。しかし1回戦の相手は、内山靖崇。同じIMGアカデミーの出身で、お互いのことを知り尽くした先輩後輩の対決は、6-1、3-6、6-3のフルセットで内山が制した。
 試合後、「初めてのツアー大会で緊張もあったし、ミスもしてしまった」と中川。第1セットでいきなり内山のサービスゲームをブレークして好スタートを切ったが、すぐにブレークバックされてイーブンに戻され、さらに2度続けてのブレークを許して第1セットを失う。それでも「第2セットからは少し落ち着いて、リズムに乗っていけた」と中川。IMGアカデミーでは『錦織に続く選手』ということで期待され、既にきっちりとしたチーム体制が組まれている中川のボールの力は強く、ライン際への正確さも持っているところは十分に見せた。
試合後、「初めてのツアー大会で緊張もあったし、ミスもしてしまった」と中川。第1セットでいきなり内山のサービスゲームをブレークして好スタートを切ったが、すぐにブレークバックされてイーブンに戻され、さらに2度続けてのブレークを許して第1セットを失う。それでも「第2セットからは少し落ち着いて、リズムに乗っていけた」と中川。IMGアカデミーでは『錦織に続く選手』ということで期待され、既にきっちりとしたチーム体制が組まれている中川のボールの力は強く、ライン際への正確さも持っているところは十分に見せた。
しかし、やはりまだまだフィジカルがジュニアのレベルを出ていない分だけ、身軽さはあっても、特にサービスでのボールの重さがなく内山を押し込めなかった。とはいえ、未完成の段階でここまで戦える力を示せるというのはやはり並ではない。サービスだけで言えば同じ時期の錦織よりも上で、ストロークもかなりのレベルにある。フィジカルがつけば、ついた分だけ強くなる可能性を見せた。この時期の選手は半年もあれば別人のようになることもある。今後も目が離せない成長株なのは間違いない。
- 2019年3月配信コンテンツ
> “FEDERER 100 WINS” R.フェデラー通算100勝の軌跡 ミラノ室内の優勝からすべてがスタートした - 2018年10月配信コンテンツ
> 楽天ジャパンオープンで準優勝! 『自信』を取り戻した錦織 圭 “新たな武器”の発表が いよいよ迫ってきている!! - 過去のコンテンツはBACK NUMBERページよりご覧頂けます。

